データから読み解いた内容を伝える技術
投稿者:Ryosuke Imai (SRE CTO)
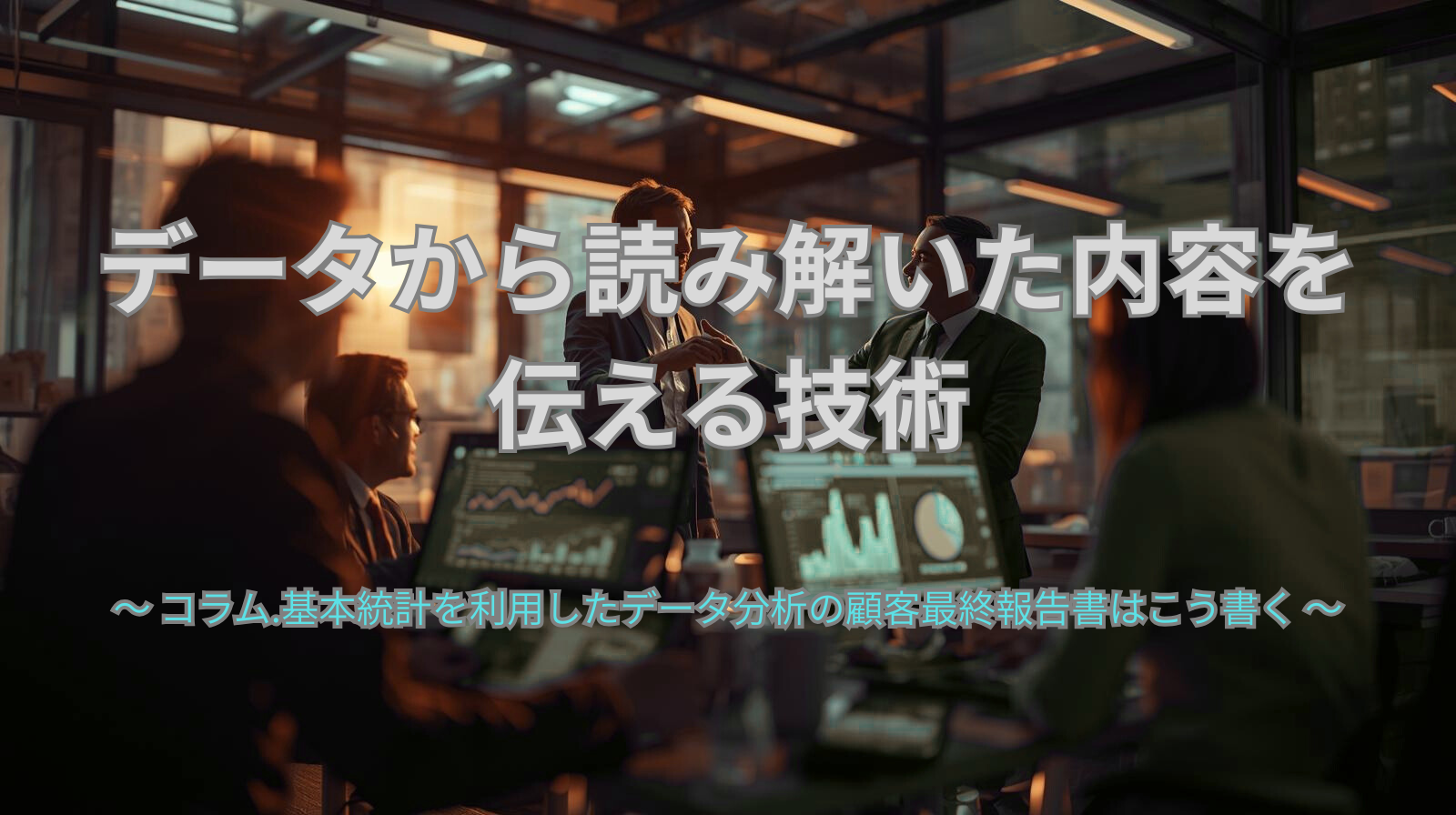
データサイエンティストにとって
データ分析の最終目的は「ビジネスの意思決定を支�援すること」 です。
そのためには、分析結果をどのように顧客に届けるかが重要です。 このコラムでは、基本統計を利用したデータ分析の最終報告書のフォーマットとポイントを解説します。
やみくもにすべてのデータや可視化を詰め込むのではなく、「伝えるべき内容」と「伝え方」 に焦点を当てます。 一番重要なのは、顧客が理解しやすい形で情報を提供することです。
まずは全体構成を整理する
まずは、最終報告書の全体構成を整理します。 雛形があると便利ですので、以下のようなフォーマットを参考にしてください。
1. はじめに
- 目的と背景
- 分析の概要
2. 分析で使用するデータの概要
- データソース
- データの前処理
3. (各分析章)
- 使用した分析手法
- モデルの選定理由
- 分析結果と示唆
4. 結論
- まとめ
- 今後の展望
データ分析の目的は、ヒアリングや要件定義を通じて明確にされます。定期的にコミュニケーションを通じて進捗を共有し、フィードバックを得ることが重要です。フィードバックで得られた内容は、必ず最終報告書に反映させましょう。
各セクションのポイント
報告書の各章で伝えるべきポイントを整理します。
「1. はじめに」は簡潔に分析方針の合意内容を再定義する場所
分析開始時にキックオフやヒアリングを行っている場合は、そこで得られた情報をもとに今回の分析の目的や背景を整理します。
この分析によって何が解決されるのか、どのような価値が提供されるのかを明確にします。
お客様と分析者の間での 「目的のすり合わせ」 は、やりすぎぐらいに丁寧に行うことが重要です。
具体的には、以下のような点を整理します。
- どのビジネス課題に対してアプローチしているのか
- 期待される成果や効果
- 分析結果をどのように活用できるのか
データ分析の目的は、ヒアリングや要件定義を通じて明確にされます。定期的にコミュニケーションを通じて進捗を共有し、フィードバックを得ることが重要です。

「2. 分析で使用するデータの概要」はデータのサマリや前処理・特徴量エンジニアリングの方針を示す場所
ここでは、データ分析で利用するデータについて整理する場所です。
具体的には、有効な分析をする上でどのようなデータを利用するのか定義し、注意すべき点を整理します。
また同時に、データの前処理や特徴量エンジニアリングの方針を示します。
具体的には、以下のような点を整理します。
- 使用するデータソースの特性や件数
- 有効なデータとしてどのくらいあるのか
- データの欠損値や外れ値の有無
- データの前処理手法(欠損値処理や外れ値処理など)
- 特徴量エンジニアリングの方針(新たな指標や特徴量の作成や不要な特徴量の削除など)
具体例を以下に示します。
以下は、ECサイトの顧客データを分析する際の具体例です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| データソース | - 顧客マスタデータ(10,000件) |
| - 購入履歴データ(過去1年分、25,000件) | |
| - アクセスログデータ(過去3ヶ月分、500,000件) | |
| 有効データの整理 | - 有効な顧客データ: 9,850件(重複除外後) |
| - 有効な購入履歴: 24,780件(返品・キャンセル除外後) | |
| - 欠損値: 顧客の年齢データが約5%欠損 | |
| 前処理の方針 | - 年齢の欠損値は中央値で補完 |
| - 購入金額の外れ値(平均±3σ)は分析対象から除外 | |
| - アクセス時間は時間帯別に集約 | |
| 特徴量エンジニアリング | - 顧客の年代別セグメント(20代、30代、40代、50代以上)を作成 |
| - 平均購入単価を算出 | |
| - 最終購入からの経過日数を算出 |
これらの前処理により、顧客の購買行動パターンを多角的に分析できる状態に整えました。
前処理の具体的な計算や判断基準が分析に多大な影響を与えるような場合は、補足資料として巻末で説明します。
「3. (各分析章)」は具体的にどのような分析と結果から、個別の考察を示す場所
この章では、当初の目的に合致した分析とその結果を報告します。
可視化や統計的手法を用いて、データの傾向やパターンを把握し、ビジネス上の意思決定に役立つ洞察を提供します。
推測統計や機械学習など、より高度な分析手法が必要な場合は、その手法の選定理由や適用方法、結果の確からしさ も明確に説明します。 この場合、仮説を立てて検証するアプローチが重要です。
このドキュメントでは、基本統計を基軸にしたデータ分析の報告書を前提としているため、上記の内容は割愛します。
【フォーマットと書き方のポイント】
基本統計の報告は、以下の4つの要素で構成するのが基本です。
-
目的の提示: なぜこのデータを集計するのかを簡潔に述べます。
-
集計結果の提示:(分析方法によって必要があれば)
- 数値データ(量的変数): 要約統計量(平均、中央値、標準偏差、最小、最大など)を表で示します。
- カテゴリデータ(質的変数): 各項目の件数(度数)と割合を表で示します。
-
結果の可視化: 表だけでは伝わりにくいデータの分布やばらつきをグラフで補足します。
-
考察(示唆): 集計結果から「何が言えるのか?」をビジネスの観点で解釈し、次のアクションに繋がる可能性(仮説)を述べます。
これらを繰り返しながら、分析目的に沿って必要なデータを網羅的に報告します。
この「考察」こそが、データサイエンティストの腕の見せ所です。
「事実の羅列」で終わらせず、「だから何なのか(So What?)」 を常に意識して下さい。
また、章の中の分析の順序や説明の流れも重要です。
分析はサマリから入り、詳細に掘り下げていく形が基本です。分析の順序も、「概要 → 詳細」 の流れを意識しましょう。
実際に報告書の具体例を以下に示します。
【】は、上記の4つの要素に対応しています。
※報告書には【】は含めない方が見やすいです。
2.1. ユーザー属性の概観
2.1.1. ユーザーの年齢分布
【1. 目的の提示】
まず、本アプリを利用しているユーザー層の全体像を把握するため、登録ユーザーの年齢分布を確認します。これにより、主要なターゲット層や、今後アプローチすべき年齢層を検討する基礎情報とします。
【2. 集計結果の提示(表)】
ユーザーの年齢に関する要約統計量は以下の通りです。
表1: ユーザー年齢の要約統計量
| 統計量 | 値 |
|---|---|
| データ件数 | 15,240件 |
| 平均値 | 42.5歳 |
| 標準偏差 | 13.2歳 |
| 最小値 | 18歳 |
| 25%点(第1四分位数) | 32歳 |
| 50%点(中央値) | 38歳 |
| 75%点(第3四分位数) | 53歳 |
| 最大値 | 85歳 |
【3. 結果の可視化(グラフ)】
年齢の分布をより直感的に理解するため、ヒストグラムを作成しました。
図1: ユーザー年齢のヒストグラム (グラフの説明: 横軸に年�齢、縦軸に人数(度数)をとったグラフ。20代後半と50代前半に山のピークが見られる。)
【4. 考察(示唆)】
事実の描写
平均年齢は 42.5 歳である一方、中央値は 38 歳であり、平均値よりも低い値となっています。これは、一部の高齢ユーザーが平均年齢を引き上げている可能性を示唆しています。
標準偏差は 13.2 となっており、年齢のばらつきは比較的大きいと言えます。
ヒストグラムを見ると、分布に2つの山(二峰性)が見られます。具体的には、20代後半〜30代前半と、50代前後にそれぞれピークが存在します。
解釈とビジネスへの示唆
主要ターゲット層の二極化: 本アプリのユーザーは、アクティブな若年層(20〜30代)と、時間的に余裕のあるシニア層(50代〜)という、大きく2つのグループに分かれている可能性があります。
施策への展開(仮説)
若年層向けには「体験型アクティビティ」や「SNS映えスポット」の特集、シニア層向けには「歴史・文化施設」や「ゆったりとした周遊コース」の提案など、ターゲット層ごとに最適化されたコンテンツ配信が有効であるという仮説が立てられます。
平均年齢の 42.5 歳だけを見て「40代がメインターゲット」と判断するのは誤りであり、各セグメントのニーズを深掘りする必要があります。
2.1.2. 人気観光スポットの傾向
【1. 目的の提示】
ユーザーがアプリ内でどの観光スポット情報に興味を持っているかを明らかにするため、各スポットページの閲覧数(PV数)を集計します。これにより、コンテンツの強み・弱みを把握�し、今後のプロモーションやコンテンツ拡充の方向性を定めます。
【2. 集計結果の提示(表)】
スポット別PV数の上位10件は以下の通りです。
表2: 観光スポット別PV数ランキング(上位10件)
| 順位 | スポット名 | PV数 | 全体に占める割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 〇〇城 | 18,520 | 15.2% |
| 2 | △△美術館 | 11,250 | 9.2% |
| 3 | □□温泉街 | 9,870 | 8.1% |
| 4 | 〇〇寺 | 7,300 | 6.0% |
| 5 | ××渓谷 | 5,110 | 4.2% |
| ... | ... | ... | ... |
【3. 結果の可視化(グラフ)】
上位スポットのPV数を比較するため、棒グラフを作成しました。
図2: 観光スポット別PV数(上位10件)
(グラフの説明: 横軸にスポット名、縦軸にPV数をとった棒グラフ。〇〇城が突出して高いことがわかる。)
【4. 考察(示唆)】
事実の描写
「〇〇城」のPV数が突出して多く、全体の**15.2%**を占めています。
2位の「△△美術館」も1万PVを超えており、高い関心を集めています。
上位には「〇〇城」「〇〇寺」といった歴史的建造物が多くランクインしています。
解釈とビジネスへの示唆
キラーコンテンツの存在: 「〇〇城」は本市の観光における強力なキラーコンテンツであることがデータから裏付けられました。この強みを軸にしたプロモーション展開が効果的と考えられます。
潜在ニーズの発見: 2位に「△△美術館」が入っていることから、歴史的建造物だけでなく、アートやカルチャーへの関心も高いユーザー層が存在することが伺えます。
施策への展開(仮説)
「〇〇城」と「△△美術館」を組み合わせた周遊モデルコースを提案することで、ユーザーの満足度向上と市内滞在時間の延長が期待できるかもしれません。
PV数の少ないスポットについては、魅力が伝わっていない可能性があります。アプリ内で特集記事を組んだり、インフルエンサーと連携したPRを行ったりするなどのテコ入れ施策を検討すべきです。
歴史や文化に関心のあるユーザー層向けに、専門家による解説付きツアーなどの高付加価値コンテンツを企画することも一案です。
初心者データサイエンティストへのアドバイス
-
数字の羅列で終わらない
- 「平均は〇〇でした」で止めず、「この平均値は、〇〇という実態を反映していると考えられます」という一歩踏み込んだ解釈を加えてください。
-
「当たり前」をデータで裏付ける
- 「〇〇城が人気なのは知っている」と思うかもしれません。しかし、その「当たり前」をデータで定量的に示すこと、そして他のスポットと比較して「どれくらい人気なのか」を客観的に示すことが、データ分析の第一歩です。
-
次の分析への「フリ」を作る
- 基本統計から得られた示唆(仮説)は、次の詳細分析のテーマになります。「ユーザー層は二極化しているのでは?」→「では、年齢層別にクーポンの利用傾向に違いはあるか?」といった形で、分析のストーリーを繋げてください。
このフォーマットを参考に、ぜひご自身の分析結果をまとめてみてください。
「4. 結論」は個々の分析結果を踏まえたクロージング
最後に、各分析章で得られた示唆を総括し、ビジネス上の意思決定に向けた具体的な提案や次のステップを�示します。 はじめに掲げた目的がどの程度達成されたかを振り返り、今後の展望や追加分析の必要性についても言及します。
データ分析は成功がすべてではありません。失敗したことより 「次に何をすべきか」 を明確にすることが、最終報告書の重要な役割です。